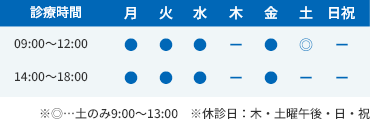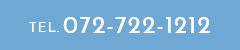かぜは、正式には“風邪症候群”といい、一般的にくしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰、発熱などを引き起こす鼻やのどの感染症のことです。
原因の約90% をウィルスが占めており、かぜウィルスは200種類以上あるとされ、どのウィルスが原因で起こったのかを特定することは困難です。
かぜは、鼻やのどにウィルスが感染することによって起こりますが、胃や腸へのウィルス感染によって嘔吐・下痢・腹痛などの腹部症状を来した状態を、俗称として“お腹のかぜ”と呼ぶこともあります。
なお、新型コロナウィルスやインフルエンザを起こすインフルエンザウィルスはかぜを起こすウィルスとは異なり、症状の重さも異なる場合もあるので、別の病気だと考えておいた方がよいでしょう。
症状
かぜウィルスの感染経路は主に飛沫感染と接触感染です。
私たちの体には、空気中のウィルスや細菌に感染しないように、侵入した異物は口や鼻、のどの粘液に付着し、線毛運動によって外に出される免疫防御機能が働いています。
侵入してしまったウィルスを体の外に追い出そうとして、くしゃみや咳、鼻水、痰が出ることになります。
ウィルスが鼻やのどの粘膜から感染して炎症を起こし、粘膜内部の組織が腫れれば、鼻づまりやのどの痛みなどの症状を引き起こします。
全身の免疫の働きがより活発になれば、発熱があらわれることになります。
こうした症状は回復までにおおむね7~10日かかり、一部の症状は3週間程度まで続く可能性があります。もともと健康に問題がある方は、肺炎に進行するなど重症化する可能性もあります。
治療
かぜの治療は、体に本来備わっている免疫力でしっかりとウィルスと戦い、自然治癒に向かえるようサポートすることが肝心です。
免疫力を落とさないように、それぞれのつらい症状をやわらげるお薬や漢方薬による対症療法が中心になりますが、免疫力が落ちてしまうことで新たに細菌がついてしまい、肺炎や副鼻腔炎などのより重い病気に移行することもあります。
そのような場合には抗生物質を併用します。
かぜをひかない習慣をつくりましょう
かぜは一年を通して見られますが、冬の冷たく乾燥した空気はかぜウィルスの飛沫が飛び散りやすくなるうえに、冬はかぜウィルスを外に追い出す線毛のはたらきが低下し、ウィルスから身を守る気道粘膜の粘液の量が減ることから、かぜは秋から春にかけて流行しやすい傾向にあります。
私たちが1年間にかぜをひく回数は3~6回とされています。
同じウィルスであってもいくつもの型があり、しかもそれが年々変異します。
一度感染したことのあるウィルスに対する免疫ができたとしても、次々に新しいウィルスに感染するため、繰り返しかぜをひいてしまいます。
日頃から十分な栄養や睡眠、適度な運動で身体の免疫力を高めるだけでなく、流行期には人混みを避け、マスクの着用や頻回に手洗いをするなど衛生面に気を配って、かぜをひかない習慣をつくることが大切です。