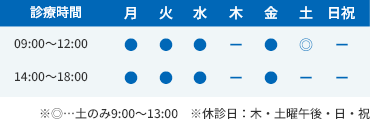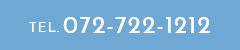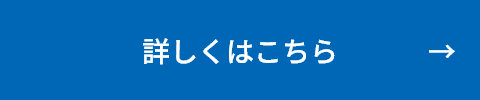循環器内科
足がむくんでいる、体重が急に増えた
お酒を飲みすぎた、長い時間座っていた、月経前など日々過ごしている中でむくんだ経験はありませんか。身体の約60%は水分でできているので、体調の変化により体に水分がたまりやすくなることがあります。原因がはっきりしていて、一時的なものであれば大きな問題はありません。しかし、なかなか治らないむくみの中には重大な病気が隠れていることもあるため、注意が必要です。
考えられる疾患
- 心不全
- 腎不全
- 肝不全
- 甲状腺機能低下症
- 静脈疾患
- リンパ浮腫
- 低栄養
- 薬剤性
動くと息切れがする
運動不足で体力が落ちると、ちょっとした動きでも息が切れてしまうことがありますよね。
会話程度の軽い動作から筋トレなどの負荷がかかる動作まで様々ありますが、いずれも身体を動かすためにはエネルギーや酸素が必要となります。このエネルギーや酸素の供給路がうまく機能しなくなった時、息切れという症状が表れます。では、どの部分の機能が低下したときに息切れ症状がでるのでしょうか。
考えられる疾患
動悸がする、脈が飛ぶ感じがする
興奮している時、緊張している時、不安を感じた時など心臓の鼓動を強く感じてドキドキすることがあります。これは、それぞれの状況に応じた自律神経の働きによるもので、正常な反応です。自律神経は身体の調子を整える働きをしており、交感神経と副交感神経の2種類がバランスを取りながら意思とは関係なく自動調節しています。
先程の例に挙げた状況では交感神経の働きが強まるため、生理的な反応として脈拍や血圧が上がります。一方で副交感神経の働きが強まるのは睡眠中や食後などの身体がリラックスしているときで、この時には血圧や脈拍は低下傾向となります。
このように交感神経による正常な反応としてドキドキすることも多くありますが、これとは関係なく動悸が起こることもあります。では動悸を感じる病気にはどんなものがあるのでしょうか。
考えられる疾患
胸が痛い、胸が締めつけられる、圧迫感がある、胸以外にも背中や顎、肩まで痛い
痛みというのは人によって感じ方が違うので、締め付けられるような痛みから圧迫感、ちくちくする痛み、違和感など様々です。また、胸には心臓や血管、肺、食道、筋肉、骨、神経、皮膚など様々な臓器があるため、胸痛で疑われる病気は数多くあります。
考えられる疾患
めまいやふらつきがある、意識が遠のくことがある
失神は、脳への血流が6秒以上途絶えた、血圧が60mmHg以下に低下したなど一時的に脳全体への血流が不足することで起こる一過性の意識障害をいいます。この意識障害は特別な処置をしなくても数秒~数分間で自然に意識は回復し、症状が残らないことが特徴です。このため、一過性の意識障害の中でも脳梗塞やてんかんなどは失神発作にはあたらず、これらの疾患とは区別されます。
考えられる疾患
歩いていると足のふくらはぎがだるくなる、痛くなる
慢性下肢動脈虚血の特徴的な症状に間欠性跛行(かんけつせいはこう)があります。じっとしているときには症状はありませんが、運動すると足の筋肉への血流不足から痛みが出現し、休むと血流不足が解消され症状が治まるというものです。さらに病状が進行すると、じっとしていても足の痛みがでてきたり、足が極端に冷たくなったり、色調が悪くなる、足の潰瘍が治りにくいなどの症状がでてきます。
考えられる疾患
健康診断で心電図異常を指摘された
心臓は電気信号が伝わることで動きます。心電図検査は、この電気信号を体表面から記録するもので、不整脈を診断したり、薬の副作用や効果判定に使用したりすることもあります。また、正常心電図との違いや以前の心電図と比較することで、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、左室肥大などの心筋疾患の診断にも役立ちます。
当クリニックで行える検査
健康診断で心雑音を指摘された
診察時の聴診で心雑音が聞こえると、弁膜症の可能性を疑います。弁膜症診断で最も有用な検査が心臓超音波検査(心エコー)です。この検査で弁膜症の部位と程度、さらには弁膜症がどれほど心臓へ悪影響を及ぼしているのかが分かります。定期的な心臓超音波検査をすることで、自覚症状がなくても悪化のサインがないか確認することができます。
考えられる疾患
健康診断で高血圧を指摘された
正常な血圧とは診察室での血圧が120/80mmHg未満、家庭での血圧が115/75mmHg未満です。では、健診で血圧が160/90mmHgと言われたらすぐに薬を飲まなければならないのでしょうか。
考えられる疾患
泌尿器科
おしっこするときに痛い
排尿時痛は、おしっこの通り道(腎臓、尿管、膀胱、尿道)に炎症があるときにあらわれ、細菌感染や粘膜の傷などによって起こります。軽い違和感やしみる感じから耐えられないほどの焼けるような激痛まで、痛みの程度は原因となっている疾患によって変わります。また、男性と女性は身体の作りが異なるため、考えられる疾患も異なってきます。
考えられる疾患
おしっこの回数が多い
頻尿とは、おしっこの回数が多いことを指します。一般的なおしっこの回数は、日中であれば5~7回程度、寝ている間であれば0回です。頻尿とは、1日を通して8回以上トイレに行くことを言います。また、夜間頻尿は就寝中に1回以上トイレに起きることされています。頻尿で悩んでいる方は年齢を問わずたくさんいらっしゃいます。しかしながら、人により体格や生活様式、水分を摂る量が違うので1日8回以上の排尿回数があるからといって、日常生活でお困りでなければ治療が必要になるわけではありません。
考えられる疾患
おしっこを出しづらい、残った感じがする
おしっこが出にくい、出始めが遅い、お腹に力を入れないと出ない、勢いが弱い、出終わるまで時間がかかる、残った感じがする、などの症状を排尿困難といいます。原因として、尿の通過する通り道が狭くなり流れにくくなっている場合と、膀胱の溜まった尿を押し出す働きが弱まっている場合に分けられます。
考えられる疾患
おしっこを出したいのに出せない
おしっこを出したいのに出すことができない、あるいはおしっこが溜まっているにもかかわらず尿意を感じないから出すことができないことで尿を全く出せない状態のことを尿閉といいます。
考えられる疾患
おしっこが我慢しにくい、漏れてしまう
膀胱に溜まった尿は、尿意に基づいて尿道から自分の意思で意図的に出すものです。しかしながら、トイレまで我慢できずに尿が漏れてしまったり、咳やくしゃみをしたときに尿が漏れてしまうことに悩んでいる方は老若男女大勢いらっしゃいます。この何かしらの原因で自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまうことを尿失禁といいます。
考えられる疾患
おしっこがたまると痛い
おしっこが溜まったり、おしっこを我慢したときに膀胱のあたりに痛みや不快感を感じることを蓄尿痛といいます。痛みの程度は軽い不快感から激しい痛みまでさまざまで、尿意切迫感や頻尿といった症状を伴うことが多く、1回あたりのおしっこの量が少なくなります。
考えられる疾患
おしっこが濁っている
正常な尿は、無色から淡黄色で透明ですが、何らかの原因によって尿が濁っている状態を混濁尿といいます。尿が濁っているからといって必ずしも異常というわけではありませんが、ほかの病気の症状の1つとしてあらわれていることもあります。
考えられる疾患
おしっこが赤い
腎臓でつくられた尿は、腎盂に集まり、尿管を通って膀胱に流れ込みます。膀胱に溜まった尿は、尿道を通って体外に排出されます。この尿の通り道やその周辺からの出血が尿に混じった状態が血尿です。
考えられる疾患
精液が赤い
精液に血液が混入し、精液が赤色調を示す状態のことを血精液症といいます。多くの場合痛みなど他の症状は伴いませんが、急な色調の変化に驚いて、心配になったり不安になる方も少なくありません。
考えられる疾患
突然腰や脇腹が痛くなった
痛みを感じる病気はさまざまありますが、古くより胆石、膵炎、尿管結石の痛みは、3大激痛といわれています。
尿管結石が尿管に詰まってしまって尿の流れが滞ると、そこより先に流れない尿は腎臓の中にまで溜まっていき(水腎症)、腎臓が急激に腫れて発作性の強い疼痛が背中や脇腹を中心に出現します。その痛みは、夜間や早朝に発作性に生じ、しばしば七転八倒の苦しみと表現されるような激しい痛みとなり、冷や汗や吐き気などの症状を伴い、救急車で搬送されることも多いです。このような発作性の痛みを疝痛発作と呼びます。
考えられる疾患
陰嚢が痛い
比較的急速に生じる陰嚢の痛みを引き起こす疾患を急性陰嚢症といいます。吐き気や嘔吐、発熱、陰嚢の腫れといった症状を伴う場合や、小さいお子さんではお腹の痛みとして訴えることもあります。
考えられる疾患
- 精巣上体炎
- 精巣捻転症
- 精巣炎
- 精巣垂捻転
- 精巣上体垂捻転
陰嚢が腫れている、左右差がある
ある日突然入浴中などに自分の陰嚢が大きくなっていることに気づかれるかもしれません。痛みがないときとあるときでは、考えられる病気は異なります。また、陰嚢の中にある精巣にしこりがあるか、硬くなっているかなどによっても考えられる病気は異なります。
考えられる疾患
陰部から膿が出ている
尿道の先から膿が出ている状態は、痛みやかゆみといった様々な不快な症状を伴うことが多く、膿は陰茎背部を尿道に沿って根元から先へ向かって押し出すことで確認できます。透明でサラサラしているものから白~黄色で粘り気が強いものまでさまざまです。
考えられる疾患
陰部に何か挟まっている感じがする、何かが触れる
女性の骨盤の中にある臓器(子宮、膀胱、直腸)を支えている骨盤底筋という筋肉や多くの靭帯が弱ってしまうと、骨盤内にある臓器が下がってくる感じが自覚されることがあり、これを下垂感といいます。骨盤内の臓器はおもに膣から下がってくることから、下腹部の違和感や下に引っ張られているように感じます。このほか、太ももの間にものが挟まったような違和感や不快感であったり、陰部に触れるとピンポン球のような丸くて硬いものが触れることもあります。
考えられる疾患
健康診断で尿の異常(潜血・タンパク尿・血尿)を指摘された
尿検査は、患者さんが採尿した尿の成分を調べることで、主に腎臓などの泌尿器の病気や糖尿病、肝臓の病気を調べる検査です。まず肉眼的に色調、混濁、浮遊物を観察し、試験紙(テステープ)を用いて、尿比重、pH、尿糖、尿蛋白(たんぱく)、尿潜血、その他(ビリルビン、ウロビリノーゲン、ケトン体)を調べます。通常、尿糖、尿蛋白、尿潜血などは、尿中には検出されない成分ですが、これらは陽性であっても自覚症状が出にくいのが特徴ですので、尿検査をすることで病期の早期発見に役立ちます。
当クリニックで行える検査
健康診断で前立腺腫瘍マーカー(PSA)が 高いと指摘された
PSA検査は前立腺がんを発見するきっかけとなる検査です。PSAの多くは精液中に分泌され、正常な状態であれば血液中に存在するPSAの量はごくわずかですが、前立腺がんになると前立腺の組織が壊れ、PSAが血液中に漏れ出して、血液中のPSAの濃度が高まると考えられています。PSA検査によって前立腺がんを早期に発見することができれば、高い生存率が見込めます。
考えられる疾患
当クリニックで行える検査
内科
発熱や咳、痰、鼻水、のどや関節の節々の痛みなどがつらい
かぜは、正式には“風邪症候群”といい、一般的にくしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰、発熱などを引き起こす鼻やのどの感染症のことです。新型コロナウィルスやインフルエンザを起こすインフルエンザウィルスはかぜを起こすウィルスとは異なり、症状の重さも異なる場合もあるので、別の病気だと考えておいた方がよいでしょう。
健康診断で血糖値が高いといわれた
糖質は生命を維持するために欠かせないエネルギー源です。しかし、低血糖や高血糖などの過度な血糖値の変動が起こると、身体を正常に保つためのバランスが崩れてしまい生命が脅かされてしまいます。通常、血糖値が上昇すると膵臓で作られるインスリンが必要に応じて分泌されるため、過度の血糖変動は起こりません。しかし、糖尿病になるとインスリンの作用不足から慢性的な高血糖状態となってしまいます。
健康診断でコレステロール値が高いといわれた
健診で脂質異常症のチェックをするのはどうしてでしょうか。これは、脂質異常症が狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患の発症リスクに関与しているといわれているからです。脂質には様々な種類がありますが、特に冠動脈疾患の発症と関係するのは、高LDLコレステロール血症や低HDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症、non-HDLコレステロール血症です。
健康診断で尿酸値が高いといわれた
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が高い状態のことで、7.0mg/dlを超えると高尿酸血症と診断されます。尿酸は体の新陳代謝により発生する老廃物ですが、尿酸を作る量と出す量のバランスにより、一定の量に保たれるようになっています。しかし、体内で作る量が過剰に増えたり、尿や便から出す量が減ったりするとそのバランスが崩れしまい、体内の尿酸は一定量を超えてしまい、高尿酸血症となります。
足の親指の付け根が腫れて激しい痛みを感じる
痛風は、ある日突然、足の親指などの関節が赤く腫れあがり、熱を持ちながら激痛におそわれる疾患です。この症状は、前日まで何も症状がなくても急に痛みだすことが特徴で、発作的に起こることから痛風発作とよばれ、発作が起こると、「風が吹いただけでも痛い」と例えられるような歩けないほどの痛みが2~3日続きます。その後、痛みは1~2週間程度で徐々にやわらいでいきますが、正しい治療を受けずに放置していると、同じような発作が繰り返し起こり、発作を起こすたびに悪化していきます。
健康診断で貧血を指摘された
血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンが少なくなった状態を貧血と言います。ヘモグロビンは全身に酸素を送り届ける役割を果たしています。このため、貧血になると息切れや動悸、めまいなどの症状が出現します。