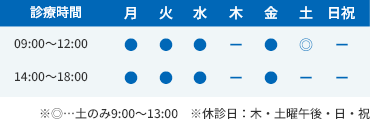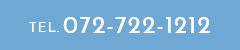尿失禁とはどんな状態?
尿失禁とは、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまうことを指します。
実に40歳以上の女性の4割以上が経験しているとされており、実際老若男女問わず多くの方が悩まされていますが、尿失禁の状態によって原因は異なります。
尿失禁の状態には大きく分けて4つの種類がありますが、そのほとんどは後述する切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁で、全体の9割の方がこのいずれかあるいは両方にあたります。
1) 切迫性尿失禁(トイレまで間に合わずに尿が漏れてしまう)
急に強い尿意を生じて我慢できなくなり、トイレまで間に合わずに漏れてしまう尿失禁です。
この急に起こる排尿を我慢できないほどの強い尿意を尿意切迫感と呼びますが、尿意切迫感や切迫性尿失禁を生じる病気が過活動膀胱です。
40歳以上の成人では12.4%に見られ、そのうち約半数の方に切迫性尿失禁が生じているとされています。
加齢や骨盤底筋(膀胱や子宮を支えている筋肉)の衰えが主な原因ですが、脳出血や脳梗塞などの脳血管障害や脊柱管狭窄症といった脊髄疾患などの神経疾患が原因として起こることもあります。
過活動膀胱の治療は、まずは水分や塩分の摂取状況の確認やカフェイン、アルコールの制限、冷え対策などの生活指導や、排尿を我慢する膀胱訓練や骨盤底筋を鍛える骨盤底筋体操の指導といっ 行動療法を行います。
それらと併せて、過活動膀胱に対する薬剤には多くの種類がありますので、患者さんごとにあった薬物治療が行われます。
このような治療においても改善が思わしくない患者さんには、ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法や神経変調療法といった新しい手術治療も検討されます。
2) 腹圧性尿失禁(咳やくしゃみをしたときに尿が漏れる)
咳やくしゃみをしたとき、走ったり飛んだりする運動をしたときや重たいものをもったとき、つまりお腹に力がかかったときに尿が漏れてしまう尿失禁を腹圧性尿失禁と呼びます。
妊娠や出産、排便時の強いいきみなどにより、骨盤底筋(膀胱や子宮を支えている筋肉)や靭帯が弱ったり緩んだりすることが主な原因です。
体重増加や便秘、重労働、喘息などの咳の多い病気による腹圧が骨盤底に負荷をかけてしまうことも原因になります。
女性の場合は経産婦さんにみられますが、男性の場合は前立腺がんや前立腺肥大症の手術後に尿道括約筋が傷付いてしまって、腹圧性尿失禁になりやすいとされています。
軽い腹圧性尿失禁の場合は、尿道のまわりにある外尿道括約筋や骨盤底筋群を鍛える骨盤底筋体操を続けていくことで改善が期待できます。
また、肥満の方には減量が有効なことがあります。
しかしながら骨盤底筋体操などの保存的治療で改善が乏しかったり、失禁量が多く早期に確実に直したい患者さんには手術治療を行います。
尿道の下に医療用のメッシュ状のテープを置いて不安定な尿道を支えるようにする手術(TVT手術やTOT手術)は、成功率は高く、体への負担も少ない手術です。
また、男性の前立腺がんの術後に生じた腹圧性尿失禁の場合には、人口括約筋を埋め込む手術を行う場合もあります。
3) 溢流生尿失禁(膀胱に溜まった尿が自分で出せずに溢れ出て漏れる)
自分で尿を出したいのに出せないがために、尿が膀胱内に溜まりすぎることで膀胱の圧力が高くなり、膀胱から尿道を介して尿が少しずつ溢れ出てきてしまう尿失禁です。少し漏れ出ると膀胱の 力は下がって漏れが止まりますが、再び尿が溜まってくると膀胱の圧力が高くなり、尿が漏れ出るという状態を繰り返します。
この溢流性尿失禁では、尿をうまく出せない尿閉という排尿障害が必ず前提にあります。
尿閉を生じる主な原因としては、膀胱機能が低下してしまい溜まった尿を押し出すことができない場合(直腸がんや子宮がんの手術後などに膀胱周囲の神経の機能が低下してしまっている状態な )と、尿の通り道である尿道が閉じてしまっている場合(高度な前立腺肥大症や尿道狭窄という尿道が狭くなっている状態)に分けられます。
溢流性尿失禁の治療では、排尿障害を改善させる薬物療法や手術療法、自力で出せずに溜まっている尿を体外へ排出させる導尿などを行います。
4) 機能性尿失禁(身体機能の衰えや認知症のせいでトイレまでたどり着けずに漏れる)
排尿機能は正常にもかかわらず、身体運動機能が衰えたためにトイレまで間に合わない、認知症のためにトイレでうまく用を足せないといった状況で起こる尿失禁です。
機能性尿失禁の治療は、尿意を感じてからトイレに行くのではなく、決まった時間に排尿する習慣を身につけることで尿失禁を減らしていくことや、介護や生活環境の見直しを含めて患者さんご の状態に応じた対応に取り組んでいく必要があります。
ポイント
- 尿失禁は、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態で、切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁で、全体の9割の方がこのいずれかあるいは両方にあたります。
- 尿失禁の原因や状態に合わせて患者さんごとに治療が提案されます。